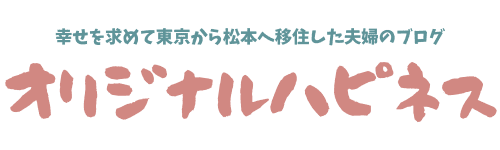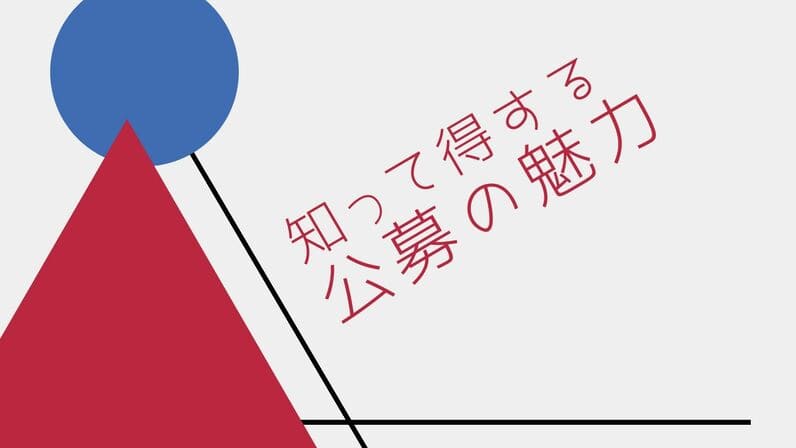こんにちは! ライターの、やまももです。
今日は、普段とちょっと違う角度から、「書くことの楽しみ」や「創造力・ライティング力の鍛え方」についてお話したいと思います。
皆さんは『公募ガイド』という雑誌をご存じですか?
だいぶ昔からある雑誌なので、名前くらいは耳にしたことがあるでしょうか? いやいや「内容はよく知らない…」という方もいるかもしれませんね。
『公募ガイド』を簡単に説明すると、日本全国の公募情報が掲載されている情報誌です。
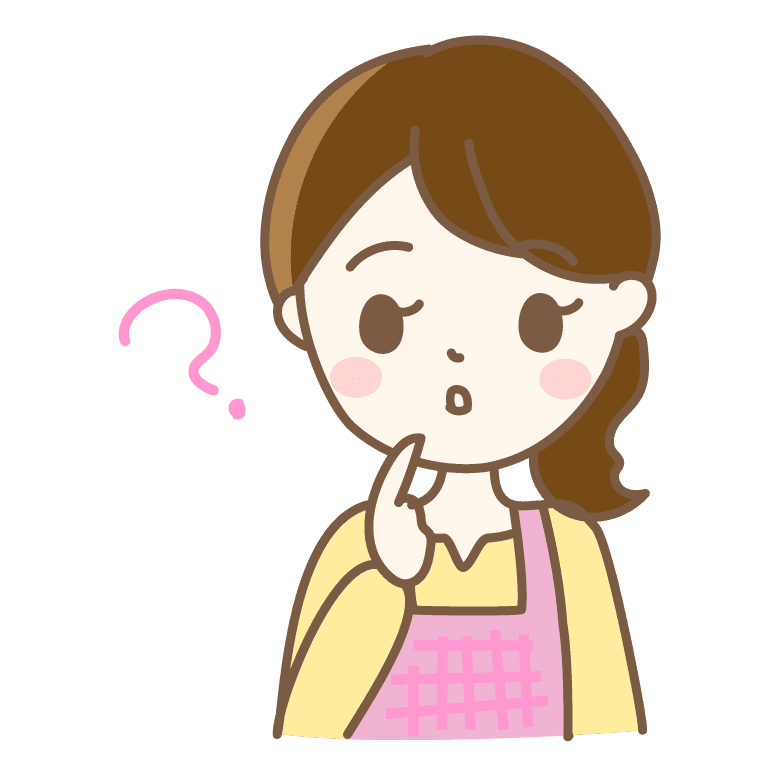
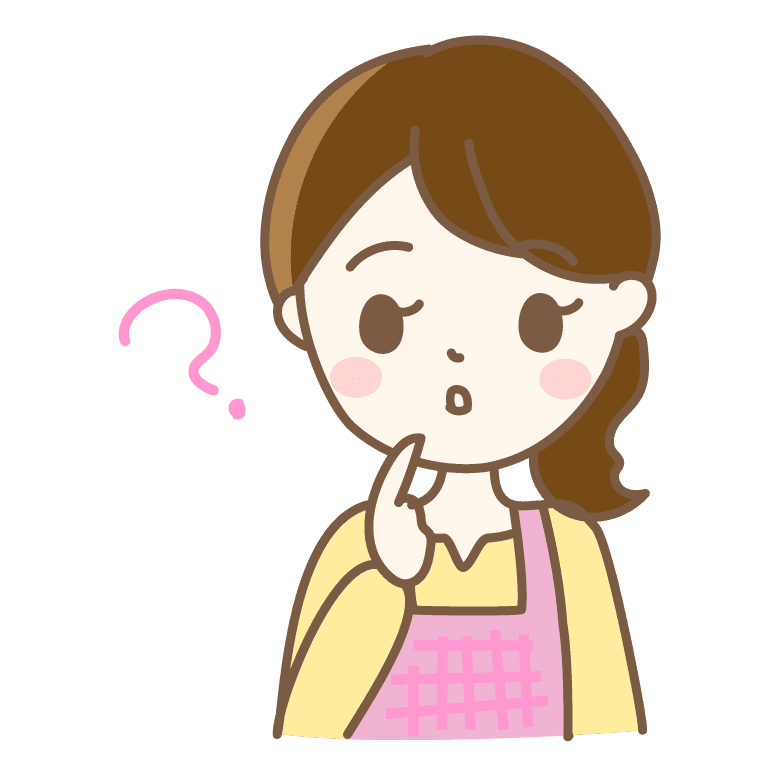
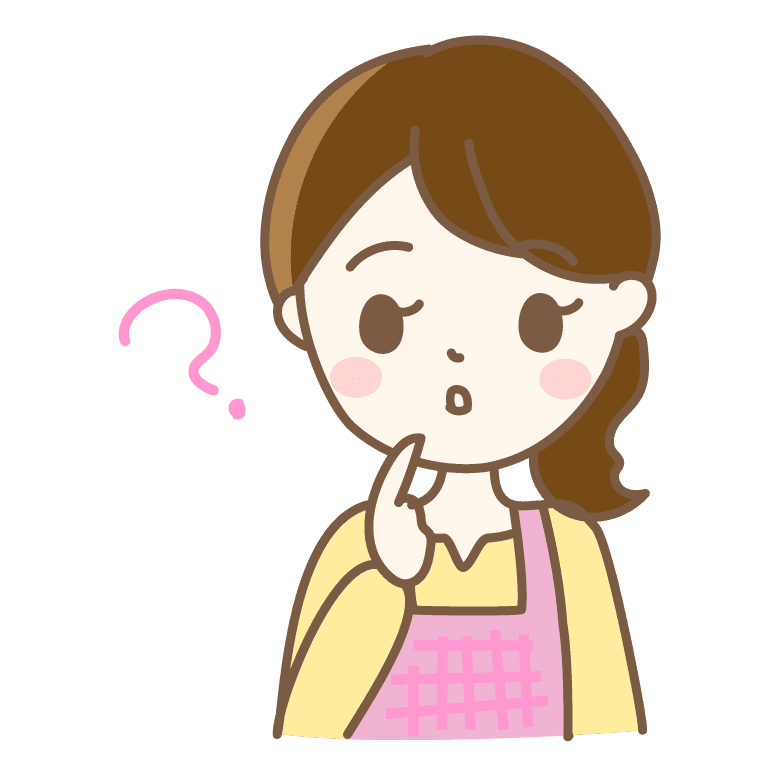
公募なんて、別に興味ないし、自分には関係なさそう…。
と思うかもしれませんが、個人的に、公募はライターとしての幅を広げていきたい人や、ライティングに必要な創造力・発想力を高めたい人などにも、かなりオススメできるものです。
そこで今回は『公募ガイド』について詳しく解説しつつ、公募の魅力と楽しみ方について紹介していきたいと思います。
『公募ガイド』についてあらためて紹介
日本全国の公募情報が掲載されている
『公募ガイド』は、日本全国で開催されている公募情報が掲載されている月刊誌です。
「そもそも公募って何…?」という方に向けて簡単にご説明すると、
公募とは「一般から広く募集すること」を意味します。
公募のジャンルは多岐にわたるのですが、『公募ガイド』上に掲載されている、おもな公募ジャンルは以下の通り。
- ネーミング・標語:交通標語、防災標語のようなものから、キャッチフレーズやコピーまで
- 川柳・俳句・短歌:お題に合わせて五七五だったり、五七五七七だったり
- 文芸:手紙や作文など気軽なものから、エッセイ、小説、シナリオ、論文など本格派のものまで
- アート:シンボルマークやキャラクターデザイン、イラスト、漫画など
- 写真・動画:テーマに沿った写真や動画作品
- ノンセクション:作詞・作曲、料理、スピーチ、アイデア、企画、モニターなど
私が最初に『公募ガイド』をパラパラとめくったときの感想は「公募ってこんなにたくさんあるの!?」でした。
よく考えれば、小説家デビューを目指す人にとっての登竜門的な文芸賞も、たいていは公募の一種なんですよね。
雑誌(月刊)とオンラインの2種類でチェックできる
『公募ガイド』は国内唯一のコンテスト情報専門誌。毎月発売される月刊誌です。
さらに、現在ではこのほかに『公募ガイドONLINE』といって、公募情報がまとめられているWebメディアでも公募情報がチェックできます。
ただ、オンラインで無料会員登録するとマイページができて、公募ガイドとの提携コンテストへ簡単に応募できたり、公募ポイントを貯めてグッズと交換できたりする魅力もあります。
ライターが公募に挑戦することで得られるもの・メリットは?
①:「書くための脳」と「創造力」が圧倒的に鍛えられる
私がフリーランスになりたての頃、年上の大先輩クリエイターさんから「公募に挑戦してみるといいよ」という話をいただだいていたのが、いまだに印象に残っています。
しかし、当時は目の前の仕事を取り、日々積み上げていくことで精一杯。
普通に「お仕事」として、クライアント企業と取引させていただくことばかりを続けていました。
ですが、このところ少し心に余裕ができてきたのもあって、自分の幅を広げるために公募情報をよくチェックしていると、数ある公募のなかでも「書くこと」に関連する案件はとくに豊富なことに気づきます。
(川柳や短歌を「書くこと」に含めるかどうかは置いておくとして…笑)
公募には「テーマ」や作品の規定(文字数など)もあるため、ある程度の縛りは設けられています。
しかし、それらは仕事の案件とは違って、基本的には自己表現の世界。
仕事であればスラスラ書けていても、自己表現となると話はまた別です。
意外と「書くことが思いつかない…」「何も浮かんでこない…」と、自分の発想力や創造力のなさにショックを受けるかもしれません(私は受けました)
でも、そんな自分に気づいて、これまで使っていなかった脳を使おう!という気にさせられました。
また、応募するにあたっての参考に過去に受賞した人の作品を読むと、ものすごく柔軟な思考やユニークな着眼点のものが多く、とても勉強になります。
別に自己表現で売れることを目的としていなくても、公募に応募すると発想力・創造力が高まるなど、得られるスキルやがたくさんあると実感しています!
②:実績づくりのチャンス
クリエイティブ作品の公募を主催するのは、全国各地の自治体や企業が中心です。
たとえば、現時点で最新の『公募ガイド(2020年11月号)』に掲載されている公募情報から、いくつかピックアップしてみます。
- 2021年度「全国統一防火標語」募集:日本損害保険協会/消防庁
- タニタ健康川柳コンテスト:タニタ
- 大樹生命の「31文字(みそひともじ)」コンクール:大樹生命保険
- わたし遺産:三井住友信託銀行
- 約束(プロミス)エッセー対象:産経新聞社
このように、誰もが知っている大手企業が主催するものが多数(上記は超一例です)
なかには何年も継続的に開催されており、それなりの知名度を誇るものもあるため、もし入賞すれば自分の実績としてアピールできるかと思います。
③:副賞がある公募が多い(賞金、特産品など)
公募への挑戦心、やる気を起こさせてくれるものすごく大きな要素があります。
それは…入選者すれば副賞として「賞金(など)」がもらえること。
「公募の賞金だからたいしたことないんじゃ?」と思いきや、詳しく見ていくと、けっこうビックリします。
なかには現金ではなくギフト券やクオカード、あるいは自治体の公募であれば特産品などの場合もありますが、それでも何かしらいただけるというのは、かなりモチベーションアップになるんじゃないかなと。
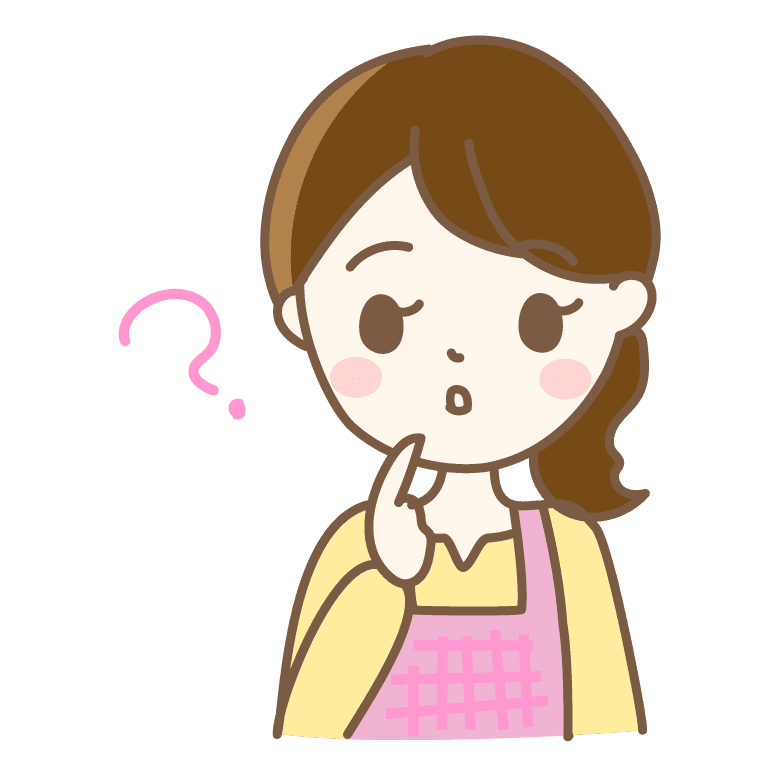
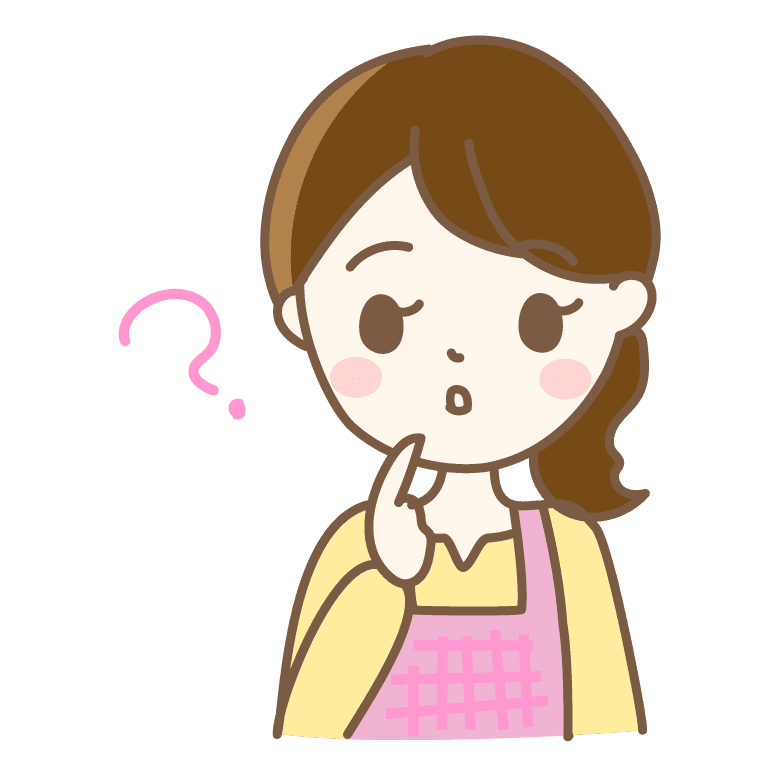
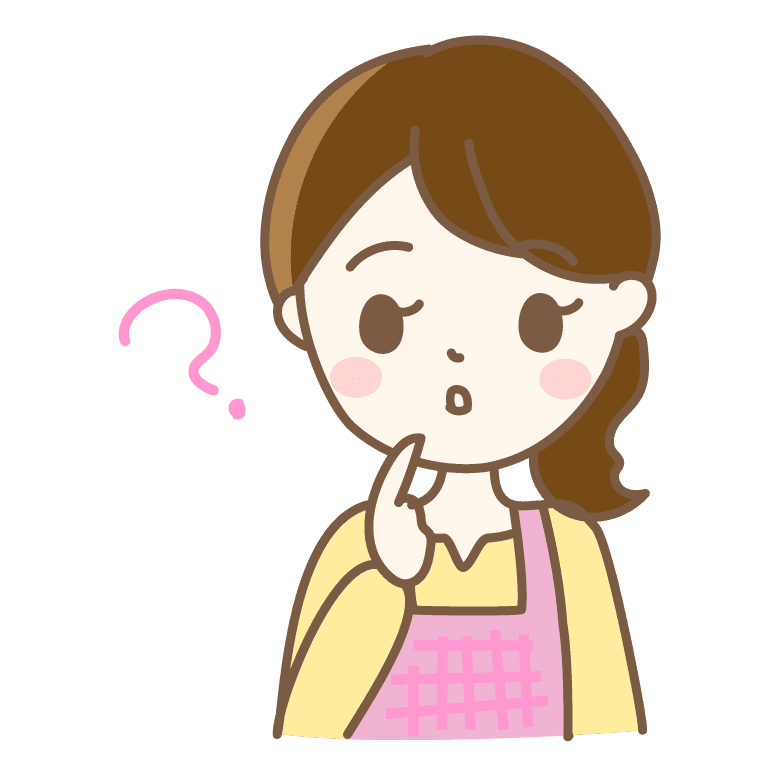
受賞なんて特別な才能がある人だけで、普通はムリじゃない?
いやいや、わかりません! 公募は誰にでも平等にチャンスがあるものですし、実際に過去の例を見ると、幅広い世代・バックグラウンドの人が受賞しています。
「読者の投稿ページ」みたいなところで読んだのですが、80歳を過ぎてもずっと公募に応募し続けて、これまでに数百万円ゲットした方もいるのだそうですよ。
楽しみながら創作をして、ついでに受賞につながったら最高ですね!
まとめ:たまには公募で違う頭を使ってみるのもオススメです
「趣味は公募」と話す人もいるくらい、昔から根強いファンがいる公募の世界。
もちろん息抜きや趣味として公募をするのもよいと思いますが、フリーランスであれば、自分の実績やスキルはどれだけあっても「これ以上いらない!」ということはないですよね。
営業活動だとか、クラウドソーシングだとかにちょっと疲れた人は、たまに公募経由で頑張ってみるのもひとつの手かと思いました。
(とはいえ公募で結果を出せば、それがそのまま仕事につながるわけではないです。あくまでもサブ的な活動として)
私の経験でいえば、仕事の案件ばかりやっていた脳を切り替えて、いきなり公募に挑戦し始めたときは「ペンが進まない…」と、気分だけは売れっ子作家みたいな状態になりました(笑)
でもいくつかやっていくと、おそらく脳が対応し始めるのかちょっとコツがつかめてきますし、頭が冴えてくると仕事のライティングもスムーズに進んだりします。
継続的に挑戦し続けていたら、いつか小さな賞でもとれるんじゃないかななんて甘い期待を膨らませつつ、引き続き公募にチャレンジしていきたいと思います。
結果発表まで数ヵ月かかるものが多いので、待ち時間もワクワクできますしね。
興味がある方は、ぜひ公募情報をチェックしてみてくださいね。