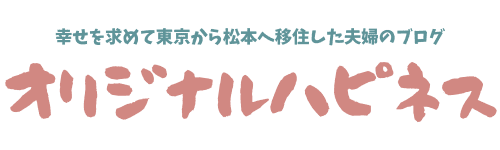PCしながら悩むサラリーマン
PCしながら悩むサラリーマン文章がうまく書けない。自分なりに文章術の本を読んだりしてがんばって書いているつもりなのに「わかりにくい」とか言われるし、実際、伝わってない気がする。
こんなお悩みに答えます。
筆者の私は、会社員・フリーランス時代をあわせて10年以上、ライター兼エディター(編集者)として働いています。人に伝わる文章を書くことについて、ずっと考え続けてきました。
「文章がうまく書けるようになりたい!」
そう思っている人はたくさんいると思います。
文章を書くスキルは、ブロガーやWebライターのように、ライティングで生計を立てようとする人だけに必要とされるものではありません。
一般的なビジネスの場でも、メールやSNS、チャットツール等で要件を伝えたり、企画書やプレゼン資料を作成したりなど、文章で誰かに何かを伝えなくてはならない場面は意外と多くありますよね。
最近では副業でWebライティングに挑戦し始めた人も増えたせいか、本屋をのぞけば文章術の本があふれています。Web上でも正しい文章の書き方を説明したページがあちこちに。
ですが、どうも「読みやすく、伝わる文章を書くこと」の本質に迫っているものはそこまで多くないように思います。
また、たとえ小手先の技術だけを覚えようとしても、その場しのぎにはなっても、なかなか別の機会には応用させにくいのではないかと感じました。
私は、わかりやすく伝わる文章を書くには、そもそも「いい文章とは何なのか?」という本質を理解することが、何よりも大事だと考えています。
そこで今回は、長年ライター/編集者として働いている私が、わかりやすく、読みやすい文章を書くための方法と考え方について、自分なりの視点でお伝えしたいと思います。
- わかりやすく、読みやすい文章が書けるようになりたい
- ライティングのテクニック本を読んだけれど、イマイチ腹落ちしない
- とにかくライティングスキルを向上させたい
- Webライターとして大切にすべきことを知りたい
こんな方におすすめの記事です。
難しい話ではありません。伝わる文章を書くための心構えやマインド面が中心なので、むしろ理解しやすいかなと。
半信半疑からでも、まずは読み進めてみていただければと思います!
わかりやすく、いい文章とは何か【大前提】
いい文章とは、「相手に意図が正しく伝わり、目的を達成できる文章」
ひとことで「文章」といっても、小学生が書く日記もあれば、若いカップルのLINEのやりとり、あるいはビジネス上でクライアントに送るメール文などもあり、文章が書かれるシーンや内容は千差万別です。
「文章はこうあるべきだ!」なんて、型にはめ込むことはとてもできません。
ただ、ここで押さえておきたいのは、誰かに向けて書かれる文章には、どんな場合でも必ず「意図」と「目的」があるということです。
だからこそ、もし「いい文章」を簡単に定義するのであれば、まずは「何のために書くのか」が明確になっており、そのうえで「目的をきちんと達成できる文章」だといえます。
具体例を挙げます。
- クライアントに送る納期連絡メール→目的:クライアントが納期を理解し、予定通りに納品してくれること。
- コンペに使うプレゼン資料→目的:競合他社に勝って、コンペに通ること。
- 好きな人に告白するLINE→目的:無事に付き合える。もしくは断られても、想いは伝わること。
- Webライターとして請け負うメディアの記事→目的:クライアントが満足し、多くの読者の目に留まること。
上記は日常で起こりうる場面を想定しましたが、どの文章にも、文章で何を実現させたいのかという「目的」があるのがおわかりいただけるかと思います。でも、目的はシーンや状況によって毎回変わってきます。
まずは何のために文章を書くのか、何を伝えたいと思っているのか、それを自問自答し、自分の腹にしっかりと落としましょう。
「そんなの当たり前のことじゃん」と思うかもしれません。
ですが、わかりやすい文章がかけていない人は、意外とこのポイントが抜け落ちていることが多いようです。
そもそも自分が何を伝えたいのか理解できていないのに、相手に伝わることはまずありません。逆に、自分の伝えたいことが明確になるだけで、不思議と文章の説得力は変わってきます。
慣れてくれば、文章を書く前に自然と「何を伝えたいのか」を考えられるようになってきます。最初のうちは、強く意識して「文章の目的(伝えたいこと)」を考えてみてください。
文章で何を伝えたいのか、相手をどう動かしたいのか、書く前に自問自答しましょう。自分でハッキリと答えを言えるくらい考えてみることが大事です。
ルールや技術の前に、「何のために書くのか」を大切に
ライティングスキルを向上させたいと思ったら、多くの人は技術的なポイントを学び、身につけようと考えるはずです。
もちろん、それも大事なことです。ですが、いくら技術を習得しようとしても、先ほど説明した「文章を書く目的=何のために書くのか」が明確でなければ、やはり相手に伝わる文章にはなりません。
一方、伝えたい思いが明確な文章は、多少の誤字脱字や変な言い回し、不自然さがあっても、なぜだかグッと胸に響くことがあります。
まずはこの本質を大切にしていただき、その上でライティングの技術やルールを身につけて、ご自身の書く文章に活用してほしいです。
わかりやすい文章を書くためのポイント6つ
ここからはわかりやすい文章の書き方について、もう少し実践的な解説をします。
細かなライティングのルールや技術を出そうとすればたくさん出てくるのですが、ここでも「本質」を重視した、最重要ポイントをお伝えします。
即実践可能な内容なので、まずはこれだけ意識してもらえればOKです!
①:シンプルな言い回しを心がける
わかりやすい文章の基本は、「シンプルを目指す」です。
文章に慣れていない人ほど、1文がものすごく長くなったり、いろんな要素を一気に詰め込んだりしがち。それを解消するために、まずは以下の2つのポイントを意識してください。
- 1つの文は50字以内を目安に。最大90字以内を心がける
- 1つの文で言いたいことは1つにしぼる
よくない具体例を書きますね。
わかりやすい文章を書くポイントはふたつあって、ひとつは1文をあまり長くしないことで、もうひとつは1文で言いたいことは1つにしぼることです。(※69文字)
たとえば上記の場合、以下のように直せます。
わかりやすい文章を書くポイントはふたつあります。ひとつは1文の文字数をあまり長くしないこと、もうひとつは1文で言いたいことは1つにしぼることです。
いかがでしょうか。文章を分けたことでスッキリとした印象になり、頭に入りやすいのではないかと思います。
文章が長くなればなるほど、必然的に読点(、の数も多くなり、読みづらさが増します。1文に読点が4つ以上入る場合も、長くなりすぎていないだろうかと見直してみてください。
必要のない言葉やフレーズは、思い切って削除するのも有効です。
②:何でもかんでも漢字にしない(ひらがなも積極的に使う)
わかりにくい文章を書く方にありがちなのが、やたらと漢字を多く使ってしまうことです。
- 例えば(たとえば)
- 勿論(もちろん)
- 宜しく(よろしく)
- 出来る(できる)
- 様々(さまざま)
- 有り難い(ありがたい)
- 色々(いろいろ)
- 為(ため)
- 何故(なぜ)
- 致します(いたします)
このあたりの言葉は、基本的にひらがなで書くのがベターです。
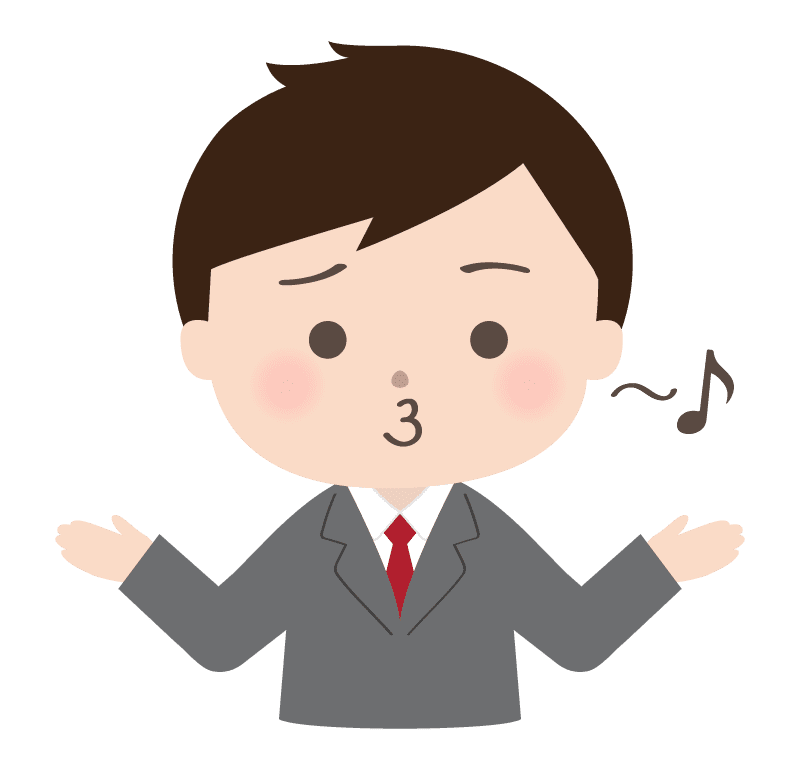
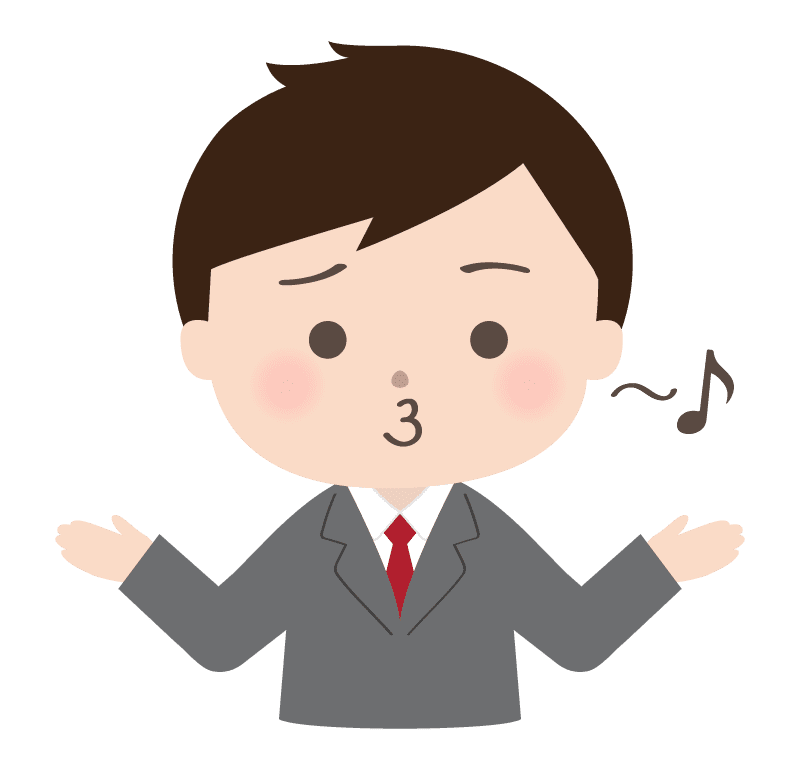
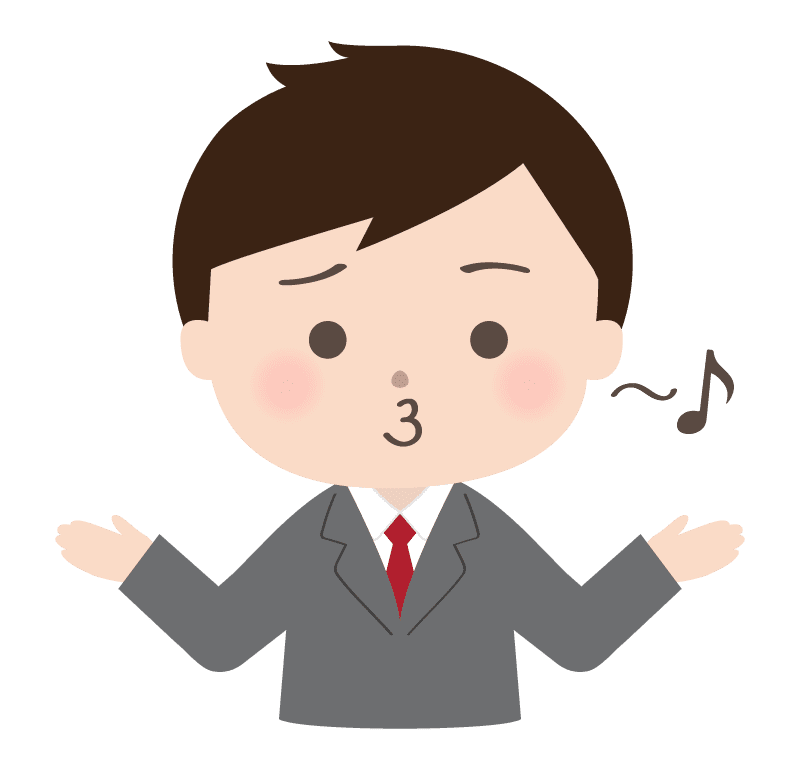
漢字でも間違ってないよね?
はい、間違いではありません。ただ、ひらがなにすることで、読み手が受ける印象は柔らかくなり、読みやすさが向上するといわれています。
このように、漢字をひらがなにすることを「ひらく」といいます。逆に、ひらがなを漢字にするのは「とじる」です。
漢字を多く使うと、それだけ文章に「堅さ」が出ます。なので、新聞の社説のような硬派な文章を書きたいときは、むしろ漢字を多くすればOK。
みなさんは、これまで研究論文のようなものを目にしたときに、わかりにくさや難解な印象を受けたことがありませんか? その理由のひとつは、論文で重視されるのは専門性や権威性だから。漢字を多用するほうが、その意図や目的を満たしやすいんですよね。
一方、日常のメール文章などで「わかりやすさ」を重視させたいときは、意識してひらくといいですよ。
また、Webライティングでは親しみやすさ、やわらかさなどが伝わりやすいように、積極的にひらくことが推奨されます。
表記に迷う言葉は、『記者ハンドブック』を使って調べることをおすすめします。
出版社などに勤務するライターは、こちらを常に手元に置いています。正しい言葉遣いをし、文章力を高めていきたい人には必須アイテム。
いわゆる「Webライター」として活動する人は持っていないケースが多いようですが、だからこそ他の人に差をつけられます。
③:同じ語尾(「です。」「ます。」など)を必要以上に連続させない
次は、丁寧に文章を書くときにやってしまいがちなミスを解説します。
それは「~です。」や「~ます。」の語尾をいくつも続けてしまうことです。
以下の例文を見てください。
わかりやすい文章を書く基本は、1文をあまり長くしないことです。
1つの文章の目安は、50文字以内です。
漢字を多用せず、ひらがなで書く言葉を増やすのがおすすめです。
文章を書く前に、文章の目的をしっかりと考えることも大切です。
上記は4つの文章が書かれていますが、すべて語尾が「です。」になっていますよね。内容は間違いではないものの、ちょっぴり稚拙で、人によっては読みづらさを感じます。
これを少し手直ししたものが、以下の文章です。
わかりやすい文章を書く基本は、1文をあまり長くしないことです。
1つの文章の目安は、50文字以内。
漢字を多用せず、ひらがなで書く言葉を増やしてください。
文章を書く前に、文章の目的をしっかりと考えることも大切です。
いかがでしょうか。同じ内容でも、語尾が連続しないように言い換えるだけでリズム感が出て、読みやすさが向上します。
慣れないうちは難しく感じるかもしれません。でも、これがスムーズにできるようになると、読む人が読んでも「お、文章書くことに慣れているな」という印象を与えられます。
ひと通り文章を書き終えたら、声に出して読み直しましょう(後ほど詳しく解説します)。やたら同じ語尾が続いている部分に気づいたら、言い換えられないか考えてみてください。
④:体言止めの連発にも注意
同じ語尾を続けないように気を配り、ちょっと文章に慣れてきた人が次にやりがちなのが、「体言止め」の連発です。



体言止め、昔学校で習ったけど、どんなのだっけ?
体言とは、「名詞」と「代名詞」を意味します。つまり、文末が名詞か代名詞になっているものが体言止めです。
先ほどの例文を再度とりあげると、以下の文章は体言止めを使っています。
1つの文章の目安は、50文字以内。(←「以内」という名詞で終わっている)
体言止めを使うメリットは、文章の流れに変化を持たせやすく、リズム感を生み出せることです。ただ、乱用するとクドさが出て逆に読みにくくなったり、違和感を覚えてしまったりしがちなので、注意してください。
体言止めは、「ここぞ!」のときにピンポイントで使うのがコツです。
⑤:余白と全体のバランスにも注意をはらう
細かな文章技術のポイントは、ひとまずここまでに解説したことをおさえてもらえればOK。
次に重視してもらいたいのが、「余白を含めた、ページ全体のバランス」に注目することです。
メールの文章でも、企画書でも、ブログ記事でも、自分で文章のレイアウトをある程度自由にコントロールできる場合には、余白を十分にとることを意識してください。
この記事も、ただ文字を書き連ねるだけであれば細かく改行をしたり、行間を空けたりする必要はありません。ただ、「ゆとりを感じてもらいたい」という想いがあるので、意識的に改行を増やしています。
人間は文字がギュッと詰まっていると心理的圧迫感を感じやすく、読みにくさを感じてしまうそうです。
でも、一部の芸能人ブログで見かけるような、異様に改行の多い文章は稚拙な印象を与えてしまうので、ほどほどが肝心です。あまりに改行が多いと、痛いポエムみたいになります(笑)
⑥:書き終わったら音読してみる(黙読でもOK)
文章全体を書き終えたら、必ず音読してください。声を出せない場であれば黙読でも問題ありませんが、慣れないうちは音読ができると、よりいいです。
音読(・黙読)の目的は、読む人の立場に立って、文章が違和感なく入ってくるかどうかを確認することです。
ライティング中は、どうしても「読む人」の視点から離れてしまいがち。そのまま文章を仕上げてしまうと主観的な内容が中心で、第三者が読むとわかりにくいものになっている可能性があります。
音読や黙読をすれば客観的な視点で文章の確認ができ、誤字脱字や言い回しがおかしなところに気づくきっかけにもなります。
読みにくいところや、突っかかったり頭に入りにくかったりする文章があれば、そこを重点的にチェックしていきましょう。もっとシンプルに書けないか、別の表現はないか、考えてみるといいですよ。
プロのライターでも、勢いよくPCで文章をうっていれば、変換ミスによる誤字脱字や言葉を使い間違えたりすることはあります。
いきなり完璧を目指さず、書き終えてからの見直しで、より精度の高い文章に仕上げればOK。
常に読み手の姿を想像(意識)しよう【シンプルだけど、大切】
ここまで、6つのポイントをお伝えしてきました。
過去に文章術やライティング技術系の本を読んだことがある方ならお気づきかもしれませんが、これ以外にも、文章の書き方や執筆ルールを細かく挙げようとすれば、まだたくさん挙げられます。
ただ、最初にお伝えした通り、そういった細かな技術やスキルは本質を理解した後に覚えていけば大丈夫です。そのほうがずっと応用が利きます。
繰り返しになりますが、文章を書くときは、まず何のために書くのか、何を伝えたいのかという「目的」を明確にしてください。
さらに読み手の姿を常にイメージできていれば、より伝わりやすい文章になります。
文章を書くときは、たいていPCやスマホに向かって一人で作業しますよね。なので、つい読み手の姿を忘れてしまいがちなんです。
でも、完全なる個人的な日記でもない限り、どんな文章を書くときでも、必ず頭のどこかに「あの人に伝えたい」「この内容を理解してもらいたい」といった期待があるはずです。
先に紹介した6つのポイントと合わせて、伝えたい相手の姿をイメージし、どう書けばより伝わるのかを何となくでも想像してみればOKです。
文章力は数をこなすことで確実に上達しますが、やみくもに数をこなすのでは効率が悪いです。ぜひ、今回のポイントを意識しながら書くことを心がけてください。
まとめ:本質の理解で、文章のわかりやすさは格段にアップする
読みやすく、わかりやすく、そして伝わりやすい文章を書くためのポイントをまとめます。
- 【大前提】何のために文章を書くのか、誰に何を伝えたいのかを明確にする
- シンプルな言い回しで、1文を長くし過ぎない
- 何でもかんでも漢字にせず、ひらがなを積極的に使う
- 同じ語尾を続けない
- 体言止めの連発にも注意
- 余白や行間、全体のバランスに気を配り、文字だらけにしない
- 書き終わったら必ず音読(あるいは黙読)する
- 【再確認】読む人の姿を常にイメージする
難しいテクニックは紹介していませんので、一つひとつ確認しながら書いてみてください。
文章テクニック本は、何冊も読み漁る必要はありません。本質的なことにフォーカスを当てた、文章の書き方に悩んだときに役立つ本を紹介します。自分も助けられました。
今回の記事でもお伝えした、まず伝えるべきことを考える大切さを、深掘りして解説してくれている本です。文章もわかりやすく読みやすいので、完読すると、頭が整理されてクリアになる実感があります。
もうひとつは、ライティングを仕事でやるのなら、ぜひ手元に置いておきたい本。
文章の書き方についてルールを学ぶなら、この本は確実。真っ当な内容です。ライティングのことだけでなく、校正や編集、企画の立て方など、ライティングに関連する制作全般の流れが体系的にわかりますので、こういう仕事に興味がある方にもおすすめです。
ちなみに、制作工程の全体を理解しているライターはさほど多くないので、そのあたりを経験していくと評価されやすくなります。
今後も、ライティングや文章に関する情報を発信していきたいと思います。お読みいただきありがとうございました。