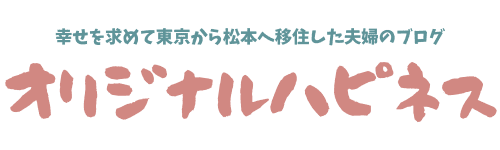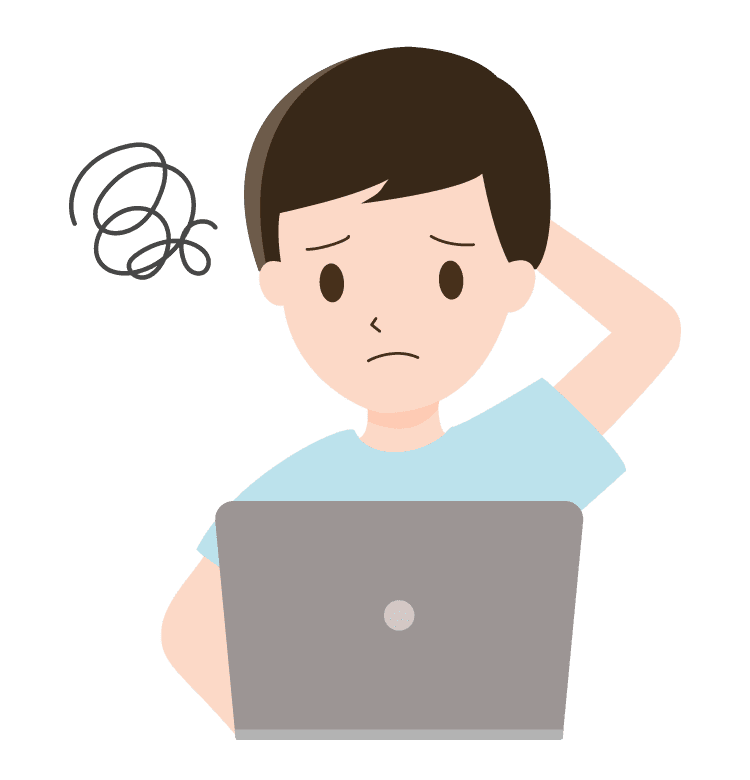 焦っている男性
焦っている男性最近、文章を書く機会が増えたけれど、どうも読んでくれる人の反応がよくない。いったい自分の何がいけないのだろうか…。
こんなお悩みに答えていきます。
こんにちは、やまももです。
出版・メディア制作会社の編集職を経て、フリーランスのライター/エディターとして9年ほど働いています。
最近ではSNSでのコミュニケーションの機会が増え、これまで以上に、文章で自分の感情や物事を伝える場面が増えていますよね。
文章力は、もはやあらゆる人が高めておいて損はないスキルです。
ただ、残念ながら文章力は一朝一夕で身につくものではありません。正しい知識を取り入れて、しっかりと意識しながら訓練していくことが大切。
私はこのブログのさまざまな記事を通して、多様な角度から文章力を高める訓練の方法や、良い文章を書くコツ・ポイントをお伝えしていきたいと考えています。
さて、今回のテーマは「文章力がないと思われてしまう文章の特徴とは?」です。
これまでに、私は数多くの駆け出しライターさんが書いた文章チェックに携わるなかで、執筆に慣れていない人がやりがちな要素があるのに気付きました。
その経験から、いくつかのポイントをきちんと押さえて書けていると「読みやすい、伝わりやすい文章」に一歩近づくと考えています。
この記事の目的は、よくない事例を取り上げつつ改善すべき点をお伝えし、文章力アップにつなげてもらうこと。ですから、どこに注意すればいいのかも解説します。
- 自分が書く文章にイマイチ自信がない
- ライティング初心者を脱却したい
- 文章力アップのためのポイントを知りたい
こんな方には、ぜひ参考にしていただければと思います。
「文章力がない」と思われてしまう文章の特徴【改善方法は?】


①:句点「。」の使い方が正しくない(「打ち言葉」はビジネスではNG)
「文章力がないな」と思われやすい文章の特徴のひとつが、「句点」を正しく打たないこと。(句点は、いわゆる文末の「。」を意味します)
この背景にあるのが、LINEやSNSなどのテキストチャットの普及で使われるようになった「打ち言葉」とされています。
打ち言葉とは?
(「話し言葉」「書き言葉」に対して)携帯電話やパソコンのキーを使って(打って)書かれた語句・語法。また、その文章。メールに使われる絵文字・顔文字や「アケオメ(明けましておめでとう)」などの略語による簡略化した表現や、漢字を多用するなどの特徴があるとされる。
goo国語辞書
「りょ」「おけ」のような省略言葉をはじめ、句点を使わないのも打ち言葉の特徴のひとつ。
平成生まれの人は、10代の早いうちからテキストチャットが当たり前になった世の中で育ち「句点を打たない文字のやりとり」を自然と行っているのでしょう。
ですが、ビジネスの場でそれをやるのはNGと考えてください。
日本語の「書き言葉」では、文章の意味の切れ目を示すために句読点を打つのは昔から変わらないルールです。
ビジネスの場でメールや報告書などを作るときには、書き言葉のルールに沿って文章を書くことは「暗黙の了解」として行われています。もちろん記事作成やライティングの仕事をするときも同様です。
しかしながら、最近はその辺りの認識がごっちゃになってしまっているのか、ビジネス上でも打ち言葉を混ぜてしまう人がいます。
改善方法
よく考えてみると、一般的な書籍や雑誌、Webサイトの記事の文章にも句点は当たり前のように付けられていますよね。
ビジネスとして文章を書くときは必ず句点をつけましょう。
プライベートでは自由にすればよいとは思いますが、ビジネス以外のメールやLINEなどでも、句点があったりなかったりする文章が混ざっているのは、文章に慣れている人が気にするポイントです。
あまりに多いと「文章力が低いな…」と思われやすいので要注意。
②:まわりくどい表現が多い
わかりやすい文章にするには、できるだけ「シンプル」を目指すことが大切。
しかし文章を書くのに慣れていない人ほど、まわりくどい表現にしがちです。例を挙げますね。
文章を書くということは、自分の考えを言葉にしていくような作業でもあります。
「~という」や「~ような」「でもあります」のような回りくどい表現は「冗長表現」といいます。場合によっては使っても問題ありませんが、連発させると文章がムダに長くなります。
これをスッキリさせてみます。
文章を書くことは、自分の考えを言葉にしていく作業です。
だいぶシンプルになりましたが、「こと」も冗長表現に含まれる言葉。さらに手直ししてみると、
「文章を書く」とは、自分の考えを言葉にする作業です。
こんなところでしょうか。もちろんこれだけが正解ではありませんが、ここで言いたいのは「どんな文章も手直しできる」点です。
あまりに冗長表現が多いと読み手はイライラします。また、本当に言いたいことが伝わらない可能性も高まりますから注意すべきポイントです。
改善方法
深く考えずに文章をひと通り書いた後、全体をよく見直してみてください。
そこで「~という」「こと」「でもあります」などの冗長表現を見つけましょう。そのほとんどは、そのまま削っても問題ない場合が多いです。
他にも冗長表現の種類はいろいろとありますが、多くの人が頻繁にやってしまいがちなのがここで紹介した内容です。
まずはこの点に気をつけるだけでも文章がスッキリしますし、シンプルな文章を書く訓練になります。
③:同じ語尾が連続している
同じ語尾の連続も、文章力がない人がやりがちです。
上手な文章が書けるようになりたいと思っています。文章力を高める方法は、本やネットで勉強しています。コツをおさえて訓練すると、できるようになります。明日も頑張ります。
たとえばこんな感じ。4つの文章、すべてが「ます。」で終わっていますよね。
同じ語尾の連続は単調で、どこか野暮ったい印象を与えます。リズム感も悪く、読みづらさも感じやすいです。
改善方法
ひと通り書いてからでいいので、語尾に着目しながら読み返すことが大切。
慣れてくると文章を書きながら自然と語尾を変化させていけますが、そこまでできるのは熟練者です。
それなりに長めの文章を書いていると、おそらく3文~5文くらい同じ語尾が続いてしまっている箇所は、いくつも見つかると思います。
別の語尾に言い換えられるところはないか探して、書き直していきましょう。体言止めを使ってみるのもリズムが生まれるのでおすすめ。(ただし使い過ぎはNGです)
④:誤字脱字(変換ミス)が多い
「誤字脱字に注意!」は昔から言われることですよね。
ただ、パソコンなど電子的なデバイスで文字を打つ機会が圧倒的に増えたいま、最も気をつけるべきことは「変換ミス」です。
デバイスを使うことで、漢字を正確に覚えなくてもよくなった一方、変換ミスが起こりやすくなっています。
とくに同音異義語には要注意。
- 「勤める」と「務める」と「努める」
- 「支障」と「師匠」と「死傷」
- 「適性」と「適正」
- 「検討」と「健闘」
- 「指示」と「支持」
- 「以上」と「異常」
など。
正しく変換するには言葉の意味を理解していないとダメですが、わかっていても勢いで誤変換してしまうことがあります。
改善方法
裏技はありません。変換を注意深く行っていくことが一番の改善方法。その後、何度か読み直して確認しましょう。
漢字が合っているかどうか自信がない場合は、辞書を引いて(オンライン辞書でもいいので)調べることが大切。
そのときに役立つのが『記者ハンドブック』です。
タイトルに「記者」とついていますが、広くライティングをする人に役立つ本です。同音異義語の使い分け方をはじめ、漢字で書くべきか、それともひらがなが適しているのかといった、「読みやすい文章を書くためのルール」がまとめられています。
ライターにとっては必携アイテムですが、市販されていますから、文章力を高めたい人は一冊常備しておくと便利。
言葉の使い方を面倒くさがらずに調べていくのが、文章改善への近道です。
⑤:一つの文章に言いたいことを詰め込み過ぎている
最後のポイントは、一つの文章にいろんなことを詰め込んでしまうことです。
一文にあれこれ詰め込むと「主語・述語の関係がわかりにくくなる」「一文が長くなる」などにつながりやすく、いろんな情報が一気に入るほど、読み手は内容を理解するのが難しくなります。
書き手の思考がまとまっていなかったり、説明過剰な場合に起こりやすいパターンです。
改善方法
読みやすい文章とされる文字数の目安は、一文あたり40~50文字以内。
100文字を超える文章には、たいてい読点「、」が複数使われています。読点に着目し、文章を分けられるところがないか探してみましょう。
ただし短ければいいわけではありません。短い文章が連続すると全体的に子どもっぽい文章になってしまうため、その点にも注意が必要です。
文章力を鍛える方法:読書をしましょう【小説がおすすめの理由】
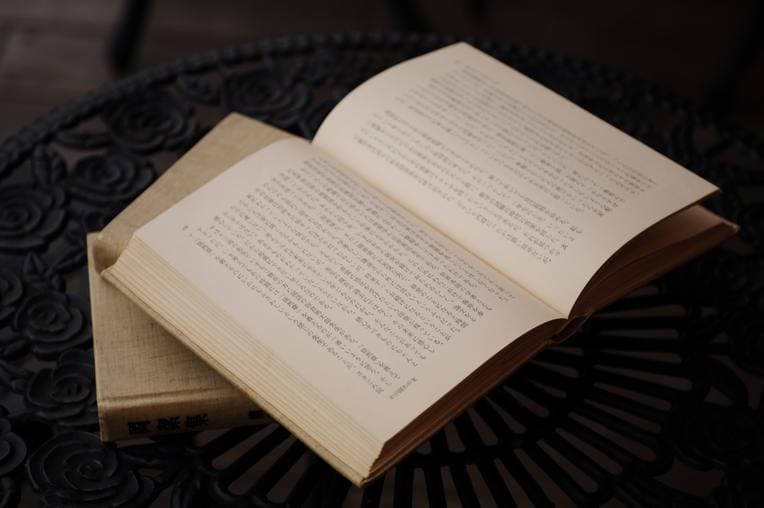
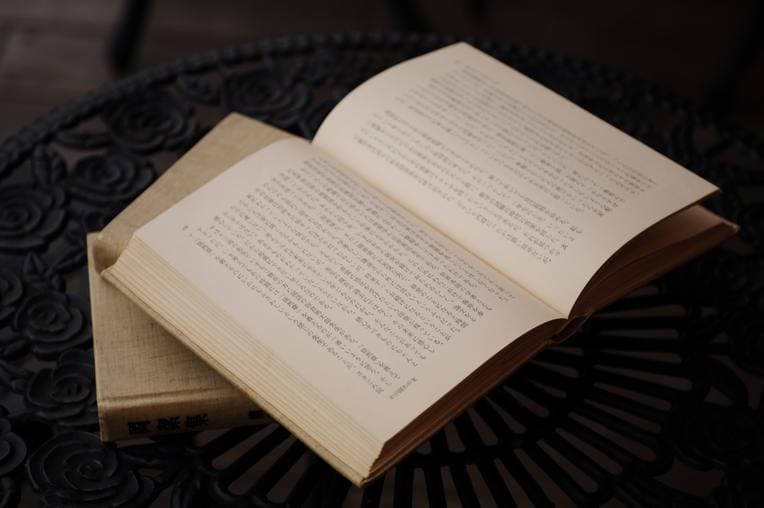
「本を読めば文章力が上がるのか?」については、いろいろな人が、自由に意見を交わしています。
私の持論は、「読書は文章力を確実に高める」です。というのも、本を読むと思考力や想像力も鍛えられ、それらの相乗効果で文章力アップにつながると考えているから。
思考力や想像力を鍛えるには「小説」が向いています。
正直、文章術やライティングのテクニック本は1冊、2冊読めば十分。どれも似たり寄ったりのことを言っていますし、テクニックを覚えたところで実践できなければ意味がありません。
それよりも、日常的に(わずかな時間でもいいので)小説を読む時間を作るのをおすすめします。
理由は、小説では「答えを見つける作業」は読者に委ねられるから。わかりやすく答えを教えてくれるビジネス本とは異なり、小説では、物語に出てくる情景や登場人物の想いなどをイメージするのは読者です。
この作業を繰り返すなかで思考力と想像力は圧倒的に鍛えられ、また豊かな表現に触れるなかで語彙力が自然と身につきます。
ただ、最近の一般人が出しているKindle本は、「文章力」の点では質が低いものも混ざっているため要注意。
それなら、ベストセラーになっている小説を読むほうが、本職の作家さんが書いた文章+編集の目がきちんと入っていますからおすすめです。
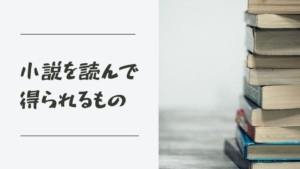
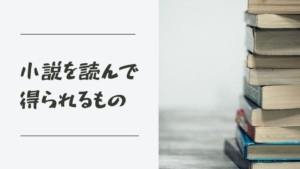
私は「文章がものすごく下手だけど日常的に読書をしている」という人に出会ったことがありません。しかし、文章が上手で読書家の人に出会うことはよくあります。
読書好き=安定した文章が書けるのは、間違いないと思います。
まとめ:ポイントをおさえて「文章力がない人」から脱却しよう
今回の話をまとめます。
「文章力がない」と一発で見抜かれやすい文章の特徴は、
- ビジネスの文章なのに、句点「。」を使っていない
- 漢字、ひらがなが極端に多い
- 「ます。」「です。」など同じ語尾が何文も連続している
- 誤字脱字と変換ミスが多い
- 一文に言いたいことを詰め過ぎており、わかりにくい
です。
いい文章を書くことは、なにも文筆業に携わる人だけの問題ではありません。わかりやすく、相手によく伝わる文章が書ければ、仕事がスムーズに進んだり人間関係がうまくいったりすることにつながります。
冒頭の繰り返しになりますが、文章力は、もはや誰もが身につけておいて損はない重要なスキルです。これまであまり気にしていなかった方は、ちょっとずつ意識してみてください。
なお、今回の記事と兄弟になるようなカタチで「いい文章を書くコツ」についても書いています。


今回と同様の内容を別角度からじっくり解説していますので、よろしければ参考にしてください。