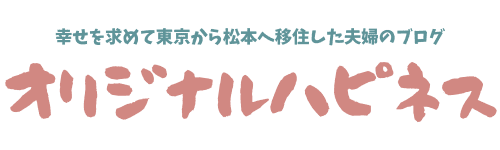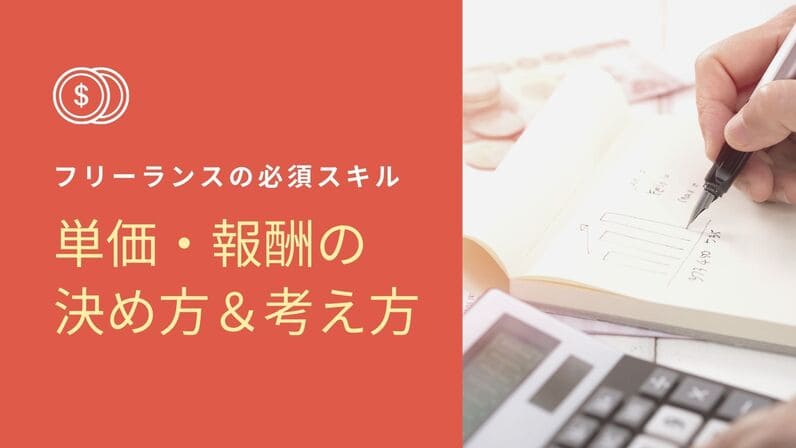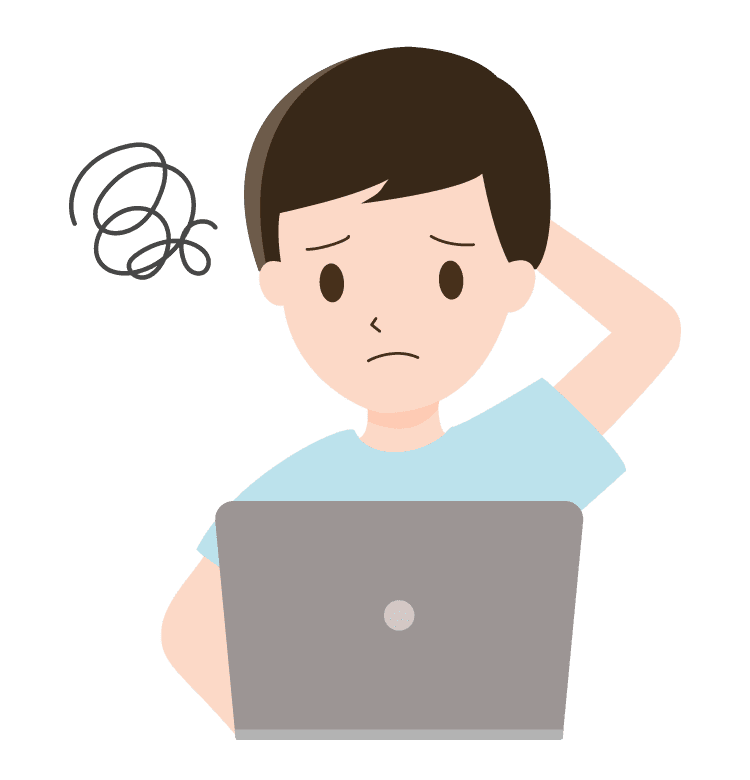 モヤモヤしている男性
モヤモヤしている男性フリーランスとして働き始めたけれど、単価や報酬の額はどうやって決めるべきだろうか…。考え方をイチから教えてもらいたい。
こんなお悩みに答えていきます。
筆者の私、やまももはフリーランス歴9年です。
私自身、単価や報酬の設定については過去に試行錯誤してきました。自分の経験も生かしつつ、わかりやすく解説していきますね。
フリーランスになると、避けて通れないのが単価・報酬(ギャラ)の設定です。
ここでいう「単価・報酬の設定」とはつまり、案件(仕事)に対して、どれくらいのお金をもらうのかということ。
フリーランスの収入は、一つひとつの仕事の報酬によって大きく変わりますから、高ければ高いに越したことはない、と考える人は多いでしょう。
ですが、あまりに高い価格を設定しても、実力がともなっていなければ案件を受注しづらいのが現実。
だからといって、低くし過ぎてもいいことはありません。
この、フリーランスにとって悩ましい単価・報酬問題。
「適正な価格の決め方を知りたい!」と、誰もが一度は悩むのが当然だと思います。
そこで今回は、私自身が長年フリーランスとして働いてきた経験から、仕事に対する価格の決め方・考え方についてアドバイスさせていただきます。
- フリーランスの単価や報酬って、どうやって決めるべき?
- 価格設定をするうえで大切な考え方
- クライアントに値切られたらどう対処・交渉すればいい?
このような内容に触れていきます。
駆け出しフリーランスの方、フリーランスを目指している方は、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
では、さっそく話を進めていきますね!
【前提】自分で値決めできるフリーランスを目指そう


「言われるがまま」の案件に慣れきってしまうのはよくない
そもそも「単価・報酬の設定」といってもピンとこない方もいるかもしれません。
というのも、フリーランスとして働く人の全員が、自分でキッチリ仕事の価格を決めているわけじゃないからです。
最近流行りのクラウドソーシングでは、発注者(クライアント)が案件に対しての依頼金額を決め、それを受注する形が一般的。
駆け出しのフリーランスは、とにかく一つひとつの仕事を取るのに精一杯で、提示された通りの単価で案件をこなしている人が多くいます。
たしかに実績がなく、本当に本当の最初の段階では、まず「受注すること」に心血を注ぐのもいいと思います。
ですがキケンなのは、その感覚に慣れきってしまうこと。
日常生活に落とし込んで考えてみてください。
コンビニやスーパーで買い物をするときも、宅配便やクリーニングなどのサービスを利用するときも、そこでは必ず(販売する側が決めた)「価格」が設定されていますよね。
消費者である私たちの気分次第で「これは〇〇円で買います」なんていうことがまかりとおる世の中ではありません。
商品・サービスを提供する側が値決めをする。
これは、ビジネスの基本です。
ですがクラウドソーシングは、クライアント側の言い値だけでサービスの価格が決まっている場合が多々あります。
もちろん、クラウドソーシングでも単価交渉をすることは可能です。
ですが、最近では「低単価でいいから受注実績をつくりたい」と考える駆け出しフリーランス(あるいは副業ワーカー)が増えているため、想像を絶するほど低単価(ライティングであれば、1文字0.1円のような)で仕事を依頼する発注者が増加しているのが実情です。
その金額が適正かを、常に考えてみよう
フリーランスとしてしっかり働いていきたいのであれば、自分の仕事を、自ら責任もって値決めできるようになるべきです。
そのために大切なのは、提示される単価や報酬に対して、その額が適正かどうかを常に考え続けること。
「とにかく受注できればいい!」と、何も考えないままになってしまうのだけは気をつけてください。
実績不足、スキル不足などでどうしても低単価で受注せざるを得ない場合も、本来はどれくらいの金額で請けるべきなのかを頭においておきましょう。
そして、1歩ずつその金額に近づくための行動をしていけば、確実に成長につながります。
フリーランスの単価や報酬の決め方・考え方


フリーランスが単価や報酬を決めていくときは、次の3ステップで考えるとわかりやすいです。
- 相場を把握する
- 自分のスキルを把握する
- 単価・報酬を時給換算してみる
それぞれについて、解説していきますね。
①:相場を把握する
単価・報酬を決めるにあたっては、やはり相場をおさえておくほうがいいです。
といっても、フリーランスの案件のギャラ相場は、あってないようなもの。
同じような仕事をしている人の情報をひたすら集めて、自分でザックリと想定すればOKです。
たとえばWebライティングの場合、クラウドソーシング上での相場は未経験者向けだと1文字あたり0.3円~0.6円、金融など専門知識が必要な案件だと1文字あたり1.5円~2円、実績豊富だと3円以上も可能…みたいな感じで、情報を集めていきます。
相場から大きくかけ離れた値決めは、最初のうちはなかなか難しいです。
まずはだいたいの相場感をおさえたうえで、次の②と③で紹介するポイントも踏まえつつ単価・報酬設定してみてください。
②:自分のスキルを把握する
スキルと単価はある程度の相関関係にあり、スキルレベルが高くなればなるほど、単価を上げていきやすくなります。
本来はもっと難しい案件をスムーズに請けられるのに、なぜか低単価の案件ばかり受注しているようでは、なかなか収入アップにつながりません。
逆に、過信して難易度の高い案件を請けてしまうと、クライアントが求める質を満たせずトラブルにつながったり、二度と依頼がもらえなくなってしまったりします。
このあたりのバランスをとるためにも、自分のスキルレベルをおさえておきたいところです。
しかし、自分のスキルを見極めるのは、職種によってはなかなか難しいです。
Web制作やプログラミング系であれば「そもそも特定のスキル(扱える言語など)がなければ案件がこなせない」ため、ある程度事前に判断できるのですが、ライティングは成果物(文章)を見ないと判断しづらいですね…。
できることなら、フリーランスとして同じ領域で先を歩いている人とつながりをつくり、現状の自分のスキルに関する意見・アドバイスをもらうことをおすすめします。
③:単価・報酬を時給換算してみる
「一見、高単価に見える案件だけれど、いざ請けてみたらものすごく時間がかかってしまった…。明らかに割に合わない…」
私は、かつてこんな失敗をしたことがあります。
この失敗の原因は、案件を完了させるのに必要な時間のすべてをきちんと把握していなかったからです。
たとえばライターの場合は、記事・原稿を書いている時間そのものだけが仕事ではありません。
案件によっては、クライアントとの事前の打ち合わせ、足を使ったリサーチ、日々の進捗報告、メールのやりとり、納品後の修正対応などなど、ライティングに付随する多様な業務が発生します。
このような工程すべてを含めて単価・報酬を考えなければ、確実に赤字になってしまいます。
正直、この辺りの判断は経験を積まないとなかなか難しいのですが、案件を完了させるために必要な行動を想定することはできるはず。
たとえばライティングでいうと、3000文字の原稿を書くにあたってどれくらいの時間がかかるのか、を考えてみることは可能でしょう。
例として、文字単価0.5円で3000文字を書く仕事を請けたとします。
1時間で書ければ時給1,500円ですが、2時間かかれば750円、3時間かかれば500円と、かかる時間によってどんどん時給は落ちていきます。
先ほど「自分のスキルを見極めるべし」と書きましたが、同じ案件であっても、スキル次第で(仕事を終えられるスピードによって)時給を上げることも下げることもできる、というわけです。
最初はピッタリいかなかったとしても、とにかく考えることが大切。やってみて、答え合わせをし、次に生かす。
これを繰り返していきましょう。
この考え方をクセづけると、「最低でも文字単価1円の仕事を請けないと時給1,000円にならないな…。30分で書けるようになれば、時給2,000円になるな…」などと、イメージできる状態になっていきます。
そのうえで、「まずは半年以内に時給2,000円以上を目指す」など、目標を立てていきましょう。
「月にいくらほしいか」から逆算して単価・報酬を決める人もいます。
ですが、相場やスキルに見合わない価格設定は失敗する可能性も高いと感じるので、私はここで紹介した①~③の順に考えていくことをおすすめします。
値切られた(希望の単価・報酬で仕事ができない)場合の対処策


金額を下げても請ける価値(メリット)があるかを考える
先に挙げた3つのポイントを踏まえて単価や報酬を提示したものの、その条件では仕事が取れずに値切られてしまう…ということもあると思います。
もしそうなった場合、どうするか。その答えは簡単です。
価格を下げても請ける価値(メリット)があるかを考えてみましょう。
ここでいう価値やメリットというのは、たとえば「報酬が少な目でもしっかりした実績になる」「継続案件の依頼につながる」「別のクライアントを紹介してもらえる」など、いろいろと考えられます。
絶対にダメなのは、値切られたりギャラが少な目だからといって手を抜くこと。
値切られて、ただ単に嫌だと感じるなら仕事を請けないほうがいいです!
というのも「嫌だな」という気持ちは、無意識にでも手抜きにつながってしまうから。
結果的にクライアントを満足させられず、自分も不快感が残り、双方にとってデメリットしかありません。
そんな仕事をするくらいなら、勉強をしたり本でも読んだりして、スキルアップに努めるほうがよほどポジティブですよね。
値切られるのは、信用を得ていない証拠でもある
常に頭に置いておきたいのは、値切られたり、こちらが適正だと思う価格で仕事を請けられないのは、100%の信用を得ていない証拠でもあるということです。
(とにかく1円でも低くしてやろう、みたいな酷いクライアントは除外するとして…)
もちろん、それ以外の理由もあるでしょう。どうしても予算がないだとか、相手にもさまざまな事情があります。
ですが、私は「値切られる=現状の自分はそれくらいの価値(スキルレベル)だ」と考えておくほうが正しいのではないかと思っています。
というのも、私自身フリーランスとしてコツコツ経験と実績を積んでいく中で、最初はクライアント主導で報酬が決まっていたのが、次第に自分主導で報酬を決められるように変わっていった感覚があるからです。
たとえば…
- 最初は安ギャラで請けていたクライアントと継続取引をするようになり、交渉をして大きくギャラアップ
- 既存クライアントからの紹介先に自分で適正な見積もり額を出し、その金額通りに受注する
など。
このような仕事の取り方は、信頼関係を積み上げていった先にこそ、できることだと考えています。
どんなに低い単価であっても、まず仕事を請けた以上は100%の力を尽くす。クライアントのニーズを満たす。
この意識をもっておくことで、確実に先につながっていくはず。
別記事でも書いたのですが、フリーランスにとって最も大切なのは、信用・信頼といっても過言ではありません。
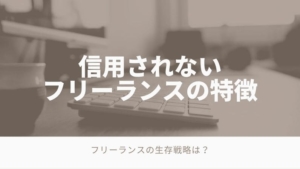
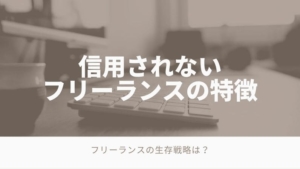
地道にやっていくほうが、長い目で見たら実は近道だったり、よい仕事ができると思います。
まとめ:実績とスキルを積み上げ、確実に単価・報酬を上げていこう
今回は、フリーランスにとって避けて通れない、単価・報酬の決め方・考え方について紹介しました。
前提として、フリーランスのギャラ設定に、絶対的な正解はありません。
まずは相場を把握し、自分の現在の立ち位置やスキルもしっかりと見極める。
そのうえで、請けた仕事の単価・報酬を時給換算したらどれくらいになるのかを必ず考える。
請けた仕事は全力で取り組む。
いろいろと考えるべきことがあって大変と感じるかもしれませんが、やっていけば感覚がつかめるようになるはずです。
基本的には「スキルを高め、実績を増やしていくほど、高い単価・報酬が得られる」と考えておくのがシンプルです。
まれに、ものすごく運がよかったり、スキルとは別の部分(人脈など)で、経験が浅い段階から高単価の仕事がとれる人もいますが、それは普通のことではありません。
フリーランスになる魅力はたくさんありますが、決して簡単なものではないです。
それだけはぜひ頭に置いて、きちんと稼げるフリーランスを目指していただけたらと思います。
お読みいただきありがとうございました!