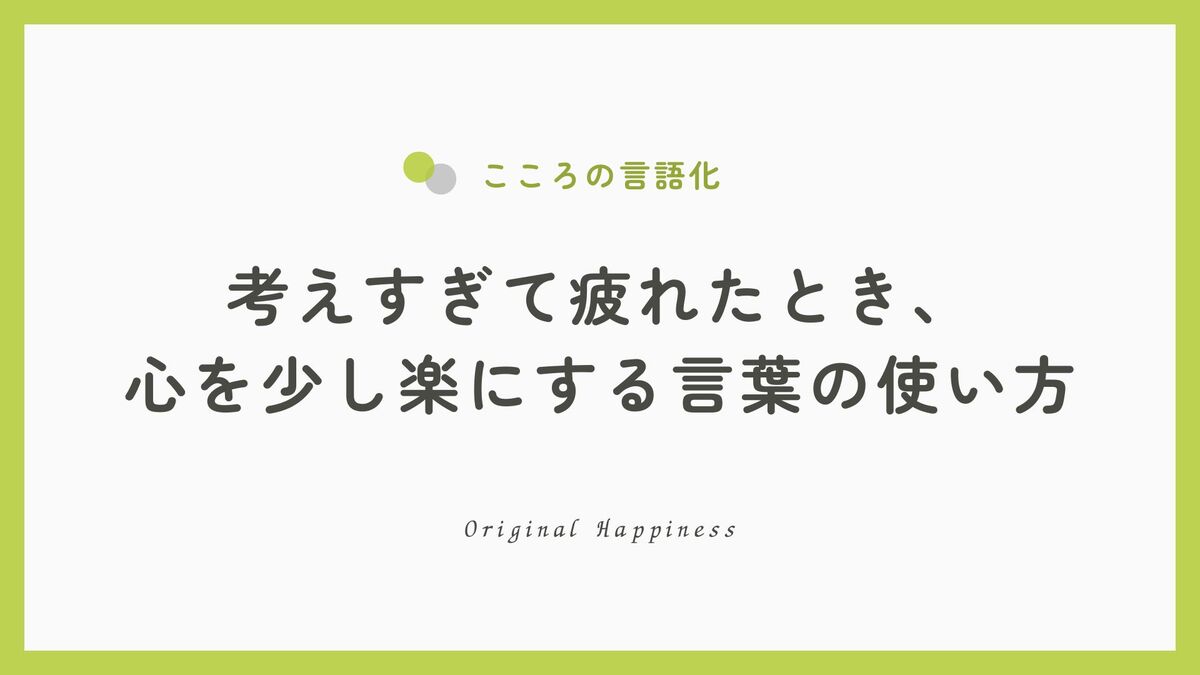こんにちは。
自分らしい働き方・生き方づくりのお手伝いをする、カウンセラーの山﨑ももこです。
私たちは、日々たくさんのことを考えながら生きています。
考えることで、新しいアイデアが生まれたり、選択や判断ができたりする。
「考える力」は、私たちにとって大切なものです。
でも、考えすぎてしまうと、気づかないうちに心や気持ちが疲れてしまうこともあります。
不安や迷いがあるとき、頭の中だけで考え続けていると、整理できないまま同じ思考を行き来したり、
「何がつらいのか、よくわからない」状態そのものがしんどくなったりしてしまうことも少なくありません。
そんなとき、まずは今の気持ちを「言葉」にしてみると、心の中が少し見えて楽になることがあります。
このコラムでは、考えすぎて疲れてしまうときに心の中で起こりやすいことと、心を少し楽にするための「言葉」の使い方についてお話します。
- つい考えすぎてしまい、気持ちが晴れないことが多い
- 頭の中がモヤモヤして、整理がつかないまま疲れてしまう
- 悩みや不安を、一人で抱え込みやすい
「ちょっと当てはまるかも」と思った方は、ぜひ肩の力を抜いて読み進めてみてください。
考えすぎてしまうとき、心の中で起きていること
「ちゃんと考えなきゃ」「間違えたくない」
そんな気持ちが強いときほど、私たちは頭の中であれこれ考え続けてしまいます。
不安や迷いを抱えたまま考え続けていると、感情と思考が絡まり合い、何が問題なのかが見えにくくなっていきます。
- 何がつらいのか、はっきりしない
- 決めたいのに、決められない
- 考えているはずなのに、前に進んでいる感じがしない
こうした状態になると、「考えが足りないのかな…」と感じてしまうこともあるかもしれません。
でも実際には考えが足りないのではなく、状況や気持ちが少し複雑に絡まっているだけ、ということもよくあります。
頭の中だけで整理しようとすると、同じ考えがぐるぐる巡り、かえって気持ちが沈んでしまうこともあります。
そんなときは、考えを頭の中に抱えたままにせず、言葉として外に出してみると、状況や気持ちが少し見えやすくなることがあります。
次からは、「言葉にする」ことで心にどんな変化が起きるのかを、もう少し具体的に見ていきます。
なぜ「言葉にする」と心が軽くなるのか
モヤモヤや気持ちの重たさが続くとき、心の中では感情・考え・過去の経験・不安などが、ひとかたまりになっていることが多いです。
その曖昧なかたまりを少しずつ言葉にしていくと、ちょっとずつ心が軽くなったり、どうすればいいかの小さなヒントが見えてくることがあります。
ここでは、実際にどんなことが起こるのかを見ていきましょう。
気持ちが整理される
言葉にしようとすると、「これは不安なのか」「それとも悔しさなのか」と、自分の内側を確かめることになります。
その過程で「あ、私、こんなふうに感じていたんだ」と、はじめて気づくこともあります。
絡まっていた状況や気持ちは、一度に全部ほどけるわけではありません。
でも、言葉にした分だけ、ちゃんと並び直されていく感覚や気づきは生まれます。
心の重荷が軽くなる
誰にも言わずに抱えていた気持ちは、気づかないうちに、毎日の判断や行動に影響しています。
たとえば、「別に大したことじゃない」と思おうとしているのに、なぜか気が散ったり、ため息が増えたりすることはありませんか。
言葉にして外に出すと、問題そのものは変わっていなくても、その気持ちに振り回される感じが少し弱まることがあります。
客観的に見つめられる
頭の中にある間は、気持ちと出来事が一体化していて、距離を取ることが難しくなります。
でも、言葉にして目の前に置いてみると、
「これは事実で、これは私の解釈」「全部が問題なわけじゃないかもしれない」と、少し引いた視点が生まれることがあります。
こうやって客観視することで、いろんなことを少し落ち着いて捉えやすくもなります。
ひとりでできる、いちばんやさしい「言葉にする」方法
気持ちを言葉にする方法は、ひとつではありません。
話すこともあれば、書くこともあります。
ただ、頭の中がごちゃごちゃしているときほど、「話そう」とすると、余計に詰まってしまうことも。
そんなときは、誰にも見せなくていい場所で、いったん書き出してみるのがおすすめです。
書き方は自由でOK
「気持ちを書き出すこと」に、正解の書き方はありません。
箇条書きでもいいし、感情のまま、ぐちゃぐちゃでまとまらなくても大丈夫。
「今日は〇〇で疲れた」「なんだかむかつく」
そんな言葉だけでも、ちゃんと心の中の言葉が出てきています。
うまく書こうとするより、いま出てきたものを、そのまま外に出す。
それだけで十分ですし、むしろそのほうが、自分の感じている本当の気持ちを見つけやすくなります。
5分だけでも効果があります
長い時間、書き続ける必要はありません。
タイマーを5分にセットして、思いつくことをひたすら紙に置いていくだけでも、頭の中の混雑が少し落ち着くことがあります。
「全部は書けなかったけど、何が引っかかっているかは見えた」
それくらいでもOKです。
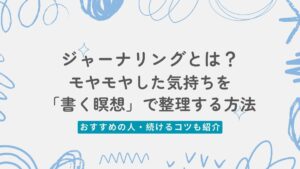
「誰かに話す」という選択肢
「書くだけでは、気持ちが整理しきれない気がする」
そんなときは、誰かに話してみることで、見えてくるものもあります。
口から言葉にして外に出すことは、ひとりで行うのとは、また違った作用をもたらします。
人に話すことで起きやすい変化
自分の心の中にあったものを人に話すと、こんな変化が起こることがあります。
✓ 自分の気持ちがもう少しはっきりする
話しているうちに、「私はこれが一番つらかったんだな」
そんなふうに、自分の気持ちが、もっとはっきり見えてくることがあります。
頭の中だけでは絡まっていた感情や思考も、声に出すことで、少しずつ整理されていきます。
✓ 「一人で抱えている感じ」が和らぐ
誰かが黙って耳を傾けてくれるだけで、張りつめていた気持ちが緩むことがあります。
問題がすぐに解決しなくても、「ここに置いていいんだ」「他の人が共有してくれる」と感じられるだけで、心の負担が軽くなるこおがあります。
✓ 自分では気づけなかった視点が生まれる
話す相手の問い返しや反応によって、これまで見えていなかった考え方に触れることもあります。
それはアドバイスというより、自分の考えを映し返してもらうような感覚に近いかもしれません。
話す相手は、誰でもいいわけではない
ただし、「話せば誰でも楽になる」というわけではありません。
「気にしすぎじゃない?」
「もっと前向きに考えたら?」
悩んでいるときにこんな言葉を受け取ると、気持ちが置き去りにされたように感じてしまうこともあります。
また、善意からの「こうしたほうがいいよ」「自分ならこうするな」というアドバイスを受けて、傷ついてしまったり、重たく感じられたりすることもあるでしょう。
もしあなたが求めているのが「整理されていない気持ちを、そのまま話して聞いてもらうこと」なら、安心して話せる相手かどうかは、とても大切なポイントです。

ひとりで抱えきれないときに、思い出してほしいこと
考えすぎてしまうときや、気持ちがうまく整理できないとき。
頭の中で考えているだけだと、不安や迷いが重なって、「何がつらいのか」さえ見えなくなってしまうことがあります。
そんなときは、無理やり答えを出そうとしたり、前向きになろうとしたりするのではなく、とにかく今の気持ちを、今のまま、言葉にしてみる。
言葉にして外に出すことで、心の中にあったものが少し距離をもって見えてきて、ちょっとだけ気持ちが軽くなることもあります。
そのために一番簡単にできる方法が「書くこと」です。
「ちゃんと考えなきゃ」よりも、「いま、何を感じているんだろう」。
まず、そんなことを意識してみてもらえたらと思います。
安心できる場で、そのままの気持ちを言葉に
自分のことを、ちゃんと考えたいと思っているからこそ、
考えすぎてしまったり、迷ってしまうこともあるのだと思います。
ひとりで考えているうちに、不安や迷いが大きくなってしまうこともあるものです。
もし、忙しい毎日に少し疲れを感じていたり、
「自分にとって大切なものが、よくわからなくなってきた」と感じることがあれば、
一度、今の状況や気持ちを言葉にしてみる時間を持ってみませんか。
私のセッションでは、今の状況や気持ちを一緒に整理しながら、
少しずつ、気持ちが楽になる方向を探していきます。
体験セッションから、気軽にご利用ください。
まずはどんなセッションか知りたい方へ